模試の復習は大事だ、ということを多くの人は聞いたことがあると思います。
ただ、模試の復習と言われても何をすればいいのか分からない人も多いと思います。
そこで、今回の記事では、私が実際に行っていた模試の復習方法を紹介していきたいと思います。
なぜ模試の復習は大事なのか?
まず最初に、模試の復習がなぜ大事なのか、私の考えを書きたいと思います。
そもそも、模試の問題は各予備校が時間をかけて作っている場合が多いため、重要な問題や良い問題が多いです。
そのため、模試で出た問題をしっかりと理解して解けるようになれば、受験で重要なところを効率的に勉強することができます。
そして、模試で出た問題をしっかりと理解して解けるようにする方法が模試の復習です。
つまり、模試の復習をすることで、受験で重要なところを効率的に勉強できるわけです。
だから、模試の復習が大事であると私は考えています。
実際、私も模試を受ける度に模試の復習をしっかりと行っていました。そのため、宅浪をして成績を伸ばすことができたと思っています。
模試を復習するタイミング
では、模試はいつ復習すればいいのでしょうか。
私は以下のタイミングで復習していました。
- 模試当日
- 模試の翌日
- 模試返却後
- 次の模試の前
次の項からは、それぞれのタイミングでやるべきことを書いていきます。
模試当日にやること
模試を受けた当日中にやることは、
(1)自己採点
(2)間違えた問題の原因や失点の原因を分析する
(3)各教科の結果を分析して、それまでの勉強の方針が正しいかどうか振り返る
この3つです。
以下、順番に解説していきます。
(1)自己採点
模試を受けたら、解答解説も配られると思うので、それを見て自己採点をして、どのくらい点数が取れているのかを確認します。
模試を受けた日なら、自分が書いた答えを覚えていると思うので、自己採点は模試当日にするのが良いです。
ただ、自己採点は、全ての教科を受け終わってからするようにしましょう。
一つの教科が終わった後にすぐに自己採点をして、その結果に一喜一憂して、次の教科に影響を及ぼしてしまうと、自分の本来の実力を測りにくくなってしまいます。
全ての教科の試験が終わるまでは、自分の実力を全て発揮することに集中しましょう。
また、記述問題など、自己採点が難しい問題は、配点の半分だけ点数をつけたり、少し厳しめに採点しておくと良いと思います。
(2)間違えた問題の原因や失点の原因を分析する
自己採点をしたら、次は、間違えてしまった問題について、なぜ間違えてしまったのかを分析しましょう。
間違えてしまった原因はいろいろあると思います。
緊張や焦り、注意不足による単純なミスだったり、理解不足や知識不足のため解けなかったりなど。あるいは、時間不足のために解けなかった問題もあると思います。
そうした原因を分析するためにも、解説をしっかり読み込みましょう。この時、余裕があれば、間違えた問題だけでなく、正解した問題の解説も読むと良いです。
ただ、試験時間内に解き終わらなかった問題に関しては、模試を受けた翌日に解くので、ここでは解説は読まなくて大丈夫です。
(3)各教科の結果を分析して、それまでの勉強の方針が正しいかどうか振り返る
自己採点をして、間違えた問題の原因を分析したら、次は各教科の結果を分析しましょう。
具体的には、どの分野で点数が取れていて、どの分野で点数が取れていないのかということや、どのような原因で失点していることが多いのかを分析するとよいです。
そのような分析をしたら、それまでの自分の勉強の方針を振り返りましょう。
もし、勉強していた分野の点数が取れていなかったら、勉強方法を見直す必要があります。
苦手な分野が見つかったら、今まで使ってきた参考書や問題集を使って復習した方がいいかもしれません。
ある教科の成績が著しく低い場合などは、その教科の勉強時間を増やしたり、その教科の勉強方法について見直す必要があるかもしれません。
単純なミスによる失点が多いのであれば、日頃からそうしたミスをしないように意識しながら勉強する必要があります。
時間内に解き終わらなかったら、時間配分を考えたり、日頃から問題を解くスピードを意識するべきです。
このように、模試の結果を受けて、日頃の勉強で改善するべきところが見つかったら、どんどん改善するようにしていきましょう。
そうすることで、勉強の効率も上がっていきます。
模試の翌日にやること
模試を受けた翌日にやることは、
(1)試験時間内に解けなかった問題を解く
(2)間違えた問題の解き直し(特に、数学、物理、化学などの理系科目)
(3)文章の音読・読み直し(国語、英語)
この3つです。
以下、順番に解説していきます。
(1)試験時間内に解けなかった問題を解く
まずは、試験時間内に解き終わらなかった問題を解きましょう。
これに関しては、模試当日中にやっても良いと思いますが、模試を受け終わって疲れている状態で模試の問題を解くのは個人的にハードだったので、模試の翌日にしていました。
模試を受け終わっても余力があるという人は、模試を受けた当日中に、試験時間内に解けなかった問題を解いても良いと思います。
(2)間違えた問題の解き直し(特に、数学、物理、化学などの理系科目)
次に、間違えた問題の解き直しをしましょう。
ただ、英語と国語に関しては、解き直しの効果があまりないと感じていたのでやらなくても良いと思います。
逆に、数学、物理、化学などの理系科目は解き直しの効果がかなりあると感じたのでやった方がよいです。
(3)文章の音読・読み直し(国語・英語)
文章の音読や読み直しも効果的です。
音読は、英語の長文と、古文、漢文ですると良いと思います。
現代文は音読ではなく、読み直すだけで十分だと思います。
音読の回数は一つの文章につき5回を目安にするとよいと思います。
現代文の読み直しは、回数をこなすよりも、理解できるまでじっくり読むことが大事だと思います。
模試返却後にやること
模試の返却後にやることは、
(1)自分が書いた答案を見直す
(2)問題の解き直し(特に、数学、物理、化学などの理系科目)
(3)文章の音読・読み直し(英語・国語)
この3つです。
以下、順番に解説していきます。
(1)自分が書いた答案を見直す
模試が返却される時に、自分が書いた答案も一緒に返却されると思うので、自分が書いた答案を見直しましょう。
特に見直すべきところは、数学の記述や、英語の記述問題、英作文、国語の記述問題などです。
自分が書いた答案を見直して、どこで点数が引かれているのかをしっかり把握して、次は同じようなことで点数を引かれないように日頃から意識するようにしましょう。
(2)問題の解き直し(特に、数学、物理、化学などの理系科目)
このタイミングでもう一度問題を解き直してみるとよいと思います。模試が返却されるのが、だいたい模試を受けてから1か月以上経つことが多いので、いい感じに模試の問題を忘れていると思います。
このタイミングで解き直すことで、模試を受けた時よりも自分がどれだけできるようになっているかを把握することができると思います。
全ての問題を解き直すことが理想ですが、時間に余裕がない場合は、模試を受けた時に間違えた問題だけでも解き直すようにすると良いと思います。
(3)文章の音読・読み直し(英語・国語)
このタイミングで、国語と英語の文章の音読と読み直しを行うと良いと思います。
さきほど書いたことと同じように、英語の長文と古文、漢文を1つの文章につき5回音読し、現代文をしっかりと理解できるまで読むと良いと思います。
次の模試の前にやること
次の模試の前にやることは、
(1)問題の解き直し(特に数学、物理、化学などの理系科目)
(2)文章の音読・読み直し(英語・国語)
この2つです。
これらに関しては、模試返却後にやることと同じなので、さきほど書いた内容を参考にしてください。
ここで、問題の解き直しや文章の音読・読み直しは何回やればいいのかと疑問に思う人がいると思います。
これに関しては、何回といった正解はありませんが、自分が問題を理解できるまで解き直したりするとよいと思います。
どうしても回数の基準が欲しいという方に向けて、回数の基準をつけるなら、3回(3セット)を目安にするとよいと思います。
まとめ
今回の記事では、私が考える効果的な模試の復習方法について紹介しました。
今回紹介した内容は、あくまで模試の復習方法の1つの例に過ぎないので、自分の勉強に取り入れられそうと思ったところはぜひ取り入れてみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
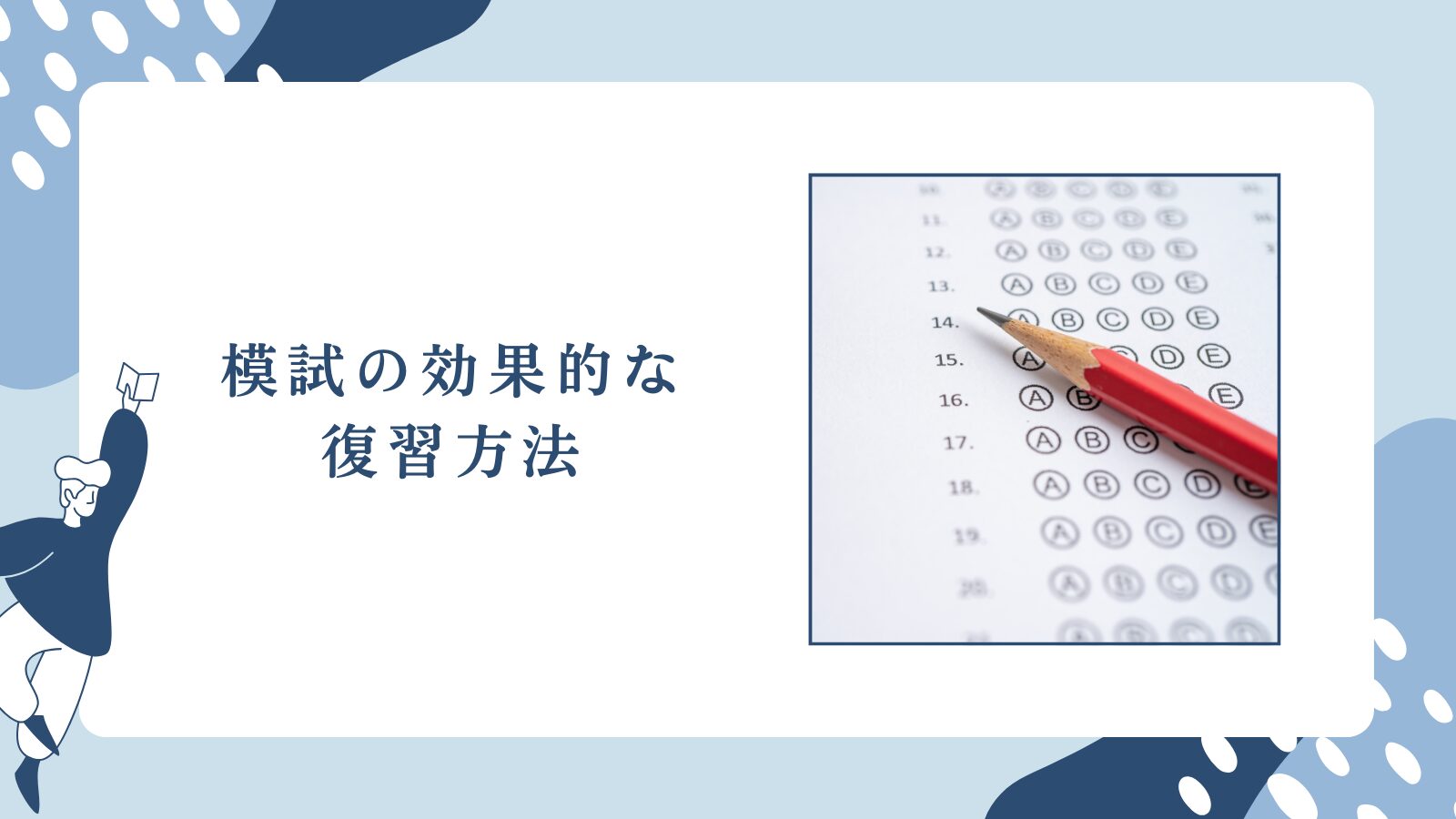


コメント