「過去問って重要ってよく聞くけど、過去問ってどうやって使えばいいの?」
このように思って、過去問の使い方が分からなかったりして悩んでいる人はけっこう多いのではないでしょうか。
私も実は過去問をどのように使えばいいのかとかなり悩んでいました。
そこで、今回の記事では、私が何回も試行錯誤をしてたどり着いた、私が考える過去問の効果的な使い方を紹介していきたいと思います。
過去問を使う目的
まず、過去問を使う前に過去問を使う目的を知っておくべきです。過去問を使う目的を知っておくことで、間違った使い方を避けることができると思います。
過去問を使う目的は主に以下の3つだと私は考えています。
①志望校の入試問題の傾向を知る
②志望校の合格ラインと現在の自分の学力の差を知る
③本番で自分の実力を発揮できるようにするため
以下、順番に解説していきます。
①志望校の入試問題の傾向を知る
過去問を使うことで、志望校の入試問題の傾向を知ることができます。志望校の入試問題の傾向を知ることで、どのような対策をすればいいのかが見えてきます。
志望校の入試問題の傾向を把握して勉強するのと把握しないで勉強するのとでは、勉強の効率が断然違います。
志望校によって頻出分野や問題の癖などが違ってきます。それに対応するためにも、過去問を使って志望校の入試問題の傾向を把握しておくと、合格するために必要な勉強が分かってきます。
②志望校の合格ラインと現在の自分の学力の差を知る
過去問を解くことで、志望校に合格するために必要な学力と現在の自分の学力の差を知ることができます。
この差を知ることによって、合格するためにはどの教科の成績を伸ばすべきなのか、また、どの分野を優先して勉強していくべきなのかが見えてきます。
逆に、この差を理解していなければ、間違った方針で勉強してしまう可能性はかなり高いでしょう。
③本番で自分の実力を発揮できるようにするため
過去問を入試本番を意識して、本番と同じ時間割で解くことで、入試本番の予行練習をすることができます。
これをしておくことで、入試本番で実力を発揮しやすくなります。
入試本番はかなりプレッシャーがかかると思うので、本番を想定して過去問を使うことで、入試当日にプレッシャーに負けてしまうということを防げると思います。
過去問を使い始める時期
過去問を使い始める時期は、基礎がある程度固まってからがいいと思います。
なぜかというと、基礎が固まっていない状態で過去問を解いても、過去問でどのようなことが問われているかを理解できない可能性が高いからです。
また、問題の解説を読んでも理解できないことも多いでしょう。
それに、基礎が固まっていない状態で過去問に挑んでも全く手も足も出ない可能性も高いです。
そのため、基礎が固まっていない状態で過去問を解いても過去問の恩恵をあまり受けることはできないと思います。
過去問は、ある程度基礎が固まってから始めるようにしましょう。
目安としては、高3の夏休みまでにはある程度基礎が固まっていて、過去問に挑める状態にすることができていると理想的だと思います。
過去問の使い方
私は、過去問を次のような2種類の使い方をしていました。
①本番と同じような、実戦形式の練習として使う
②問題集と同じように使い、何周もする
ここからはそれぞれの使い方について解説していきたいと思います。
①本番と同じような、実戦形式の練習として使う
私は主に、過去問はこの使い方をしていました。
直近の5~7年分はこの使い方をすると良いと思います。
具体的な使い方としては、まずは合格するために試験本番で取る必要がある点数、つまり、目標点を設定しましょう。
インターネットなどで調べれば、共通テストと2次試験の比率、教科の配点、合格者最低点、合格者平均点などが出てくると思うので、それをもとにして教科ごとに目標点を設定しましょう。
次に、本番を意識して、本番と同じ時間割で過去問を解くようにします。
この時、時間配分や解く順番など、得点を最大化するための戦略も意識すると良いです。
そして、この方法で過去問を1年分解き終えたら、しっかり復習と分析をしましょう。
復習をする時のポイントは、過去問で分からなかった問題や、間違えてしまった問題を今まで使ってきた参考書や問題集を使って、その問題に関係する部分だけでなく、その周辺の部分と一緒に復習することです。
このように復習するとかなり時間がかかってしまうと思いますが、自分が得意でない分野をかなり効率的に勉強できるのでおすすめです。
また、分析をする時のポイントは以下の3つです。
(1)合格するために、あとどこで何点取る必要があるのかを把握する
(2)間違えた問題について、間違えてしまった原因を分析する
(3)得点を最大化するための戦略がよかったかどうか振り返る
(1)合格するために、あとどこで何点取る必要があるのかを把握する
過去問を解いたら、信頼できる先生にお願いして、添削をしてもらうとよいです。添削を受ける環境がない場合は自己採点でも大丈夫です。
添削を受けたり自己採点をしたら、自分が過去問で取れた点数と過去問を解く前に設定した目標点と比較しましょう。そして、どの教科で点数が取れていないのか、どの分野で点数を取れていないのかを確認し、合格するためにはあと何点どこで点数を取る必要があるのかを把握することが大切です。
合格するために、あとどこで何点取る必要があるかを把握できたら、それを今後の勉強方針に活かすようにしましょう。
(2)間違えた問題について、間違えてしまった原因を分析する
間違えた問題について、なぜその問題を間違えてしまったのか、原因を分析します。ケアレスミスで間違えたのか、自分の実力不足だったのか、原因を分析したら、そのひとつひとつについて対策を考えます。
ケアレスミスで間違えてしまった場合は、次同じミスをしないようにはどうすればよいかを考えます。
実力不足で間違えてしまった場合は、どこの理解が浅くて問題が解けなかったのか、どこをもっと勉強すればその問題が解けるようになるのかを考えます。
(3)得点を最大化するための戦略がよかったかどうか振り返る
過去問を解き終わって自己採点もしたら、時間配分や問題を解く順番など、自分が考えた戦略が良かったかどうかを振り返ります。良くなかったのであれば、自分の考えた戦略をもう一度見直しましょう。
②問題集と同じように使い、何周もする
この使い方は、「東大の英語25か年」のように、簡単にたくさんの過去問が手に入る大学を志望している人に向いている使い方です。
直近の5~7年分以降はこの使い方をするとよいと思います。
また、直近の5~7年分でも、本番と同じような実戦形式の練習として使った後にはこの使い方をしてもよいと思います。
この使い方のメリットとしては、その大学の問題の傾向や癖に慣れることができる点です。
また、たくさんの問題を解くため、学力の向上も期待できます。
数学や物理、化学に関しては、全ての問題を理解して、解けるようになるまで解くのが理想です。
英語は1周するだけで十分だと思います。
※私は二次試験の勉強は数学、物理、化学、英語しかしていないので、ここでは数学、物理、化学、英語にしか触れていません。
Q&A
Q.過去問はどの年度から解くべきか?
A.最新の過去問をまず最初に解くべきだと私は思います。それ以外は特に順番はこだわらなくて良いと思います。
Q.過去問は温存するべきか?
A.直近の1~3年分は温存する必要はないと思います。直前期に解く分をとっておきたいという人は、直近の3~7年分を温存しておくとよいと思います。また、それよりも古い過去問は温存しなくてよいと思います。
Q.赤本と青本はどっちがいいか?
A.どっちでもよいと思います。好きな方を使ってください。
私が考える赤本と青本の大きな違いは、解説のレベルです。
赤本の方がレベルが少し低く、青本の方が少し高い印象があります。ただ、どっちを使っても大きな違いはないと思います。
ちなみに、私は赤本を使っていました。
まとめ
今回は私が考える効果的な過去問の使い方について書きました。少しでも過去問の使い方で悩んでいる人の役に立てればうれしいです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

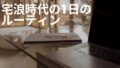

コメント